土地売却 2019/11/15
土地信託とは?手間をかけずに土地活用をするメリットとリスク

土地を活用する方法としては、貸したり、マンション経営や駐車場経営をするなどいろいろあります。しかし中には初期投資がそれなりにかかるものもあり、資金に余裕がないとなかなかできないこともあるでしょう。
そこで、手間をかけずに持っている土地を活用する方法として、土地信託という方法をご紹介します。
土地信託とはどのような仕組みで利益を得ることができるのか、またどのようなリスクに注意する必要があるのか、初めてでもわかりやすいように解説しますので、土地活用の一つの方法として検討してみてはいかがでしょうか。
土地信託とは専門家に預けて運用してもらうこと
投資信託という言葉はご存知でしょうか。
専門家にお金を預けて株などを購入してもらい運用する方法です。その土地版が土地信託だと思ってもらえれば良いでしょう。
土地を預けてプロが運用
土地の活用は素人ではなかなか難しいものです。そこで、専門家に預けて運用してもらい、収益が上がったらその一部をもらえる、という仕組み、それが土地信託です。
「信託」とは信頼をして託すことですから、財産を預けても本当に大丈夫な会社なのかが心配になると思います。
信託会社は誰でも簡単に設立できるわけではなく、信託業法により免許を受けた会社しか業務を行うことはできません。
信託会社には2種類あります。
- 運用型信託会社:会社の裁量で運用と管理を行う。免許が必要。
- 管理型信託会社:委託者からの指示によって財産の管理を行う。登録が必要。
この記事で説明する信託会社は、土地を預けて運用益を出すために動いてもらうので、運用型信託会社のことを指しています。
信託銀行でも土地活用を行なっているところがありますね。そのようなところに預けると、建物を建てて賃貸事業を行うなどして利益を出すように土地を活用してくれるのです。
ではどのような土地でも預かって運用してくれるのかというと、そうではありません。
土地信託が向いている人
では、土地信託が向いているのはどのような人なのか、例を挙げてみます。
- 土地を持っているけれど自分で管理することが難しい
- 不動産の知識が乏しくどうすれば運用できるのかわからない
- 土地を複数持っているので自分では活用しきれない
- 相続後のトラブルが心配
- 自分が認知症などになった場合の財産管理が心配
自分で土地を活用するとなると、建物を建てるにしても初期費用が必要ですし、その後の管理も大変です。
せっかく土地を持っているのにどうすればいいのかわからない、維持費だけがかさんでいくという方は是非活用の一つの手段として、土地信託を検討してみてはいかがでしょうか。
土地信託の2つの形と主な活用法
土地信託には2つの形があります。
- 賃貸型:一定期間信託したら手元に土地が返ってくる。
- 処分型:最終的には売却する。
賃貸型は一定期間預ける信託契約を結んで、信託会社に運用をしてもらいます。
運用益の中から配当金として利益を受け取り、契約期間が終わったところで土地を返してもらうのです。
一般的に土地信託というと、賃貸型を指しています。
活用法はいろいろ
では土地をどう活用するかですが、活用の方法はいろいろあります。
- アパートやマンションを建てて経営する
- ビルを建ててテナントを入れる
- 貸し会議室などを経営する
- 駐車場にする
その地域、立地によって適した活用法が違ってきますよね。
素人では事業を経営することはもちろん、適した活用法を検討することも難しいでしょう。
その点、土地信託にすればすべてお任せで活用してもらえますからとても助かりますね。
土地信託で配当金を受け取る仕組みと契約方法
では土地を預けて配当金を受け取るためにはどうすればいいのか、契約の方法や手順などについて説明します。
信託会社を選んで契約する
最初にしなければならないことは信託会社を選ぶことです。
信託業務を行える会社は決まっていますから、その中で選ぶことになります。
信託会社もしくは信託銀行で、かつ、土地信託を扱っている会社の中で信頼できる会社を選ぶことが非常に重要になってきます。
ではどうやって選ぶのか。
- これまでの実績
- 会社としての信頼性
- 土地の信託に対してどれほどの専門線があるのか
などを複数の会社で比較し、よく話を聞いた上で選ぶようにしてください。
信託の仕組みなどをわかりやすく、また、考えうるリスクなども誠実に説明してくれる会社にした方が良いでしょう。
そして1社を選んだら信託契約を結びます。契約を結ぶと土地の所有権が持ち主から信託会社に移ります。
信託会社が土地の持ち主として運用を開始し、預け主は利益が出たらその中から配当金を受け取る、という仕組みです。
契約期間
土地信託の契約期間は数ヶ月という短い期間ではなく、最低でも10年くらい、長い場合には20〜30年という期間になります。
考えてみれば当然のことで、建物を建てて運用する場合などは初期投資がかなりかかりますから、回収する期間もそれなりにかかります。
つまり、それだけの長期間、とりあえず自分では使わない土地でないと預けることができないということです。
信託期間中は契約を解除できないため、どのくらいの期間にするかも慎重に考える必要があるでしょう。
信託受益権を得る
信託会社と契約をすると、所有権が移転する代わりに、土地の所有者は「信託受益権」を得ることができます。
信託受益権とは、信託した土地から利益が出た場合にそこから配当金を得る権利のことです。この権利によって、収益が得られるようになるのです。
信託期間中は契約を解除できないと先ほど説明しました。
しかしなんらかの理由でお金が必要になることもあるでしょう。その時に土地を売ろうとしても信託期間中なら売れないわけですね。
信託会社が土地を活用する
契約したら、信託会社が土地の運用を開始します。
アパートやマンションなど賃貸物件を建てることが多いですが、立地によっては駐車場などにすることもありますし、ビルを建ててテナントを入れるということも。
その方法については信託会社にお任せなので、所有者が考える必要はありません。
運用益が出たら配当をもらう
建物を建てて運用を開始したら、徐々に収益が上がり始めます。そうなると、その中から信託受益権を持っている人に対して配当金が支払われます。
ただし、収益が上がるまでにはそれなりに時間がかかります。
それら諸々の経費となるものを支払った後に残るのが本当の収益となります。
その中から配当金を得ることになります。ですからその時の情勢によって配当額も変わってくるのです。
満期になると土地が戻ってくる
土地信託には賃貸型と処分型がありましたが、賃貸型にしておくと契約の満期とともに土地は戻ってきます。
この時に戻ってくるのは土地だけでなく、信託していた間にできたもの全てが一緒に戻ってきます。
もし建物が建っていればその建物も一緒に、そして万が一ローンが残っている場合にはそのローンも一緒についてきます。
ですからあまり短い期間では契約できないんですね。
一括借り上げとの違い
たまに「30年一括借り上げ」「家賃保証」などという広告を見かけると思います。
これは、アパート経営の会社がまとめて借り上げてくれるシステムなのですが、まとめてアパートを借りてくれるなら一見お得そうに見えますよね。
しかし契約期間が短いことと、入居の状況次第で家賃を減額される可能性があるのです。
例えば家賃が10万円の部屋が10室あるアパートを借り上げてもらい、毎月100万円の収益がある!と思ったら大間違いで、賃料の見直しのタイミングで5万円に下げられてしまう可能性もあるのです。
入ってくると思っていた収益が一方的に減らされるとローンの返済にも困ってしまうでしょう。
利益はどのくらいになる?土地信託のメリット
自分で土地を活用するよりも手間が少ないですしリスクも低いというのが土地信託の大きなメリットです。
自分で運用しなくていい
一番のメリットは、自分で土地を活用しなくても収益が入ってくるという点でしょう。
自分でアパートや駐車場を建てた場合、その維持管理が大変です。経営者として賃貸について知らなければいけないことがたくさんあります。
土地の活用は素人ではなかなか難しく、失敗すると大きな負債だけが残ってしまいかねません。
ただし、どのような会社に信託するかは自分で考えなくてはいけないので、土地信託に強い会社についての知識、情報は集める必要があるでしょう。
活用資金がいらない
自分で建物を建てるとなると、それなりにまとまった初期費用が必要になりますが、個人で行うのは大変なことですよね。
しかし土地信託なら、アパートでもマンションでも、建てるための資金は信託会社が借り入れて行うのです。
この費用を土地の所有者が負担する必要はありません。
建物がついて戻ってくる
契約期間が終了すると土地が戻ってきますが、その時には上に建っている建物も一緒に戻ってきます。
預けていた土地だけでなく、土地に付属しているものも所有者のものになるというのが大きなメリットの一つです。
もちろん、戻ってきた後は建物付きで売却することも可能です。
信託受益権を売却できる
先ほど、信託受益権が売却できるということについても説明しました。もう少し詳しく説明しましょう。
信託受益権というのは株式などと同じく有価証券の扱いになります。
元本保証はなく、リスクのある商品として取引されます。
信託受益権を売却するメリットとしては、税金が安くなるということが挙げられるでしょう。
通常、満期まで信託していて契約終了とともに土地が戻ってきた場合、土地と建物に対して不動産取得税がかかります(一定の軽減要件あり)。
税金の面でも売買するタイミングというのが重要になってきます。
リスクが低い
個人で土地を売買したり活用したりするのはかなりの労力が必要ですし、経営の知識も必要になってきます。
ある程度の初期投資もしないと建物も建てられないため、負担が大きいですね。それで経営がうまくいかなかったら大変なことになります。
相続税を節税できる場合も
信託受益権は売却できるだけでなく相続もできます。もし自分が土地を信託している間に何かあった場合、家族は信託受益権を相続することになります。
土地の相続には様々な手続きが必要ですし、相続税もそれなりにかかります。
しかし信託受益権は土地の相続よりも手続きが簡単な上、場合によっては節税できる可能性もあります。
利益が出ない可能性も。土地信託のデメリット
低リスクで簡単に行える土地活用というメリットがある反面、リスクが低いということは利益も低いということです。
自分で経営している場合よりも収益は少なくなってしまうというのは致し方ないことかもしれないですね。
収益から信託報酬を引かれる
収益が上がった場合に、そこから信託報酬が差し引かれます。
これは、不動産会社を通じて土地を売った時に払う仲介手数料と同じようなものです。代わりに運用してくれているのですから、ある意味当然ですね。
自分で土地を管理するよりの収益性は下がってしまいますが、その分安心して運用を任せられるのですから、リスクが低いという点では仕方のないことでしょう。
一定期間でも所有権を移転する必要がある
名目上の所有権を一時的とはいえ信託会社に移さなくてはいけません。
本当に戻ってくるのか?もし信託会社が倒産したら、土地も没収されてしまうのでは?と心配になる方もいるのではないでしょうか。
その点は安心です。預けた土地は信託会社の固有財産から外されていますので、債権者に差し押さえられてしまうことはありません。
これを「信託の倒産隔離機能」といい、強制執行されることはないのです。
建物のローンも一緒についてくる
万が一ですが、建物のローンが残っている場合、契約終了とともにそのローンも引き継ぐことになります。
そうならないように、ローンを返済し終わった後に期間が満了するような契約にしておく必要があるでしょう。
必ずしも収益は上がらない
収益が上がっても、そこからローン分など必要経費が引かれます。それらが全て引かれた上で、残った分が配当金ということになりますから、必ずしも配当金がもらえるという保証はないのです。
ローン返済中は当然利益も低くなってしまいますので、いつぐらいから配当金が上がり始めるのか、それはどのような運用をしてもらえるかにかかってくるわけですね。
最初のうちはなかなか収益は上がりませんので、辛抱が必要でしょう。
どう活用するかを全てお任せにした以上は信じて待つしかない、というところです。
土地信託で注意すべきポイント
土地信託の仕組みはお分りいただけたと思います。そこで、初めて土地信託をする方に注意してほしいポイントについてもまとめました。
会社選びが成功のカギ
土地信託は、必ずしも成功するわけではなく、思っていたような利益が上がらないこともあります。
成功させるためには何といっても会社選びが重要!
自分の土地をどのような会社なら有効活用してくれるのか、その会社の強みを比較検討し、最も適した会社を選ぶことが土地信託成功へのカギとなります。
自分が直接運用するわけではないにしても、まずは土地活用について基本的なことは勉強してみることをおすすめします。
そうしないと、話を聞いてもどの会社が適しているのか判断できないからです。
基本的なことを学んだ上で、複数の会社の話を聞いて、どの会社が一番自分の土地をうまく活用してくれるだろうかということを判断してください。
全ての土地が信託できるわけではない
土地を持っていれば全て信託できるかというと、そうではないのです。
当然ですが、信託会社が「利益が出る」と判断した土地しか引き受けてはもらえません。
収益が上がらないような土地を引き受けても損をするだけだからです。
それならばさっさと宅地として売ってしまった方が良いという判断もできますね。
土地信託はリスクもあるが手間なく土地を活用できる方法
土地信託は100%利益が出ると保証されているものではありませんが、低リスクで土地活用ができる方法です。
信託会社に聞いてみて、もし活用できるとなったら、そのままにしておくよりも預けて運用してもらった方が少しでも配当金を受け取れる可能性があります。
自分で活用するよりも手間がかかりませんので、放置している土地があるなら土地信託を検討してみてはいかがでしょうか。







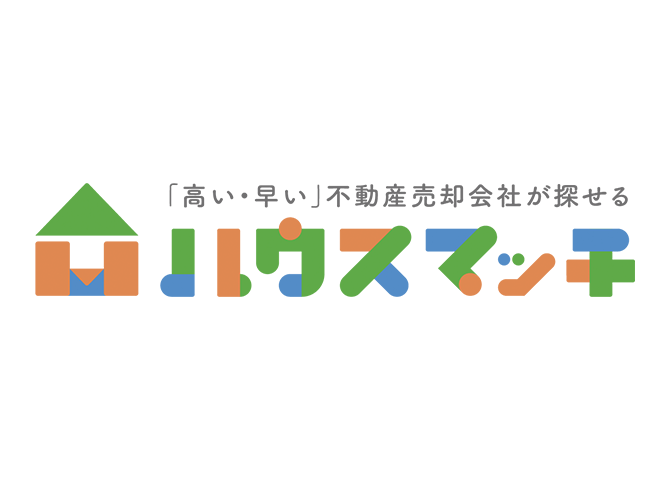
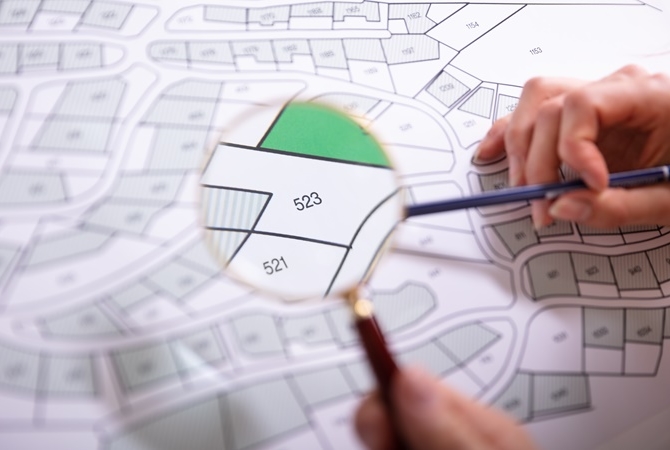



 専門のコンシェルジュがお手伝いいたします!
専門のコンシェルジュがお手伝いいたします!
