土地売却 2019/11/15
農地バンクを賢く利用してみよう!メリットや活用法まとめ

農地は勝手に売ったり買ったりできず、また、勝手に家を建てることもできません。ですから、持っていてもどう活用したらいいのかわからないという方も多いでしょう。
そこで利用したいのが農地バンクです。農地バンクは公的な制度ですから安心して使えますし、今持っている農地を有効活用できるようになるかもしれません。
農地バンクとはどのような制度なのか、使い方やメリットなどについてまとめました。
使って安心!農地バンクは公的な制度
農地は売るのも貸すのも難しい。ということで発足したのが農地中間管理機構というところです。
これが通称「農地バンク」なんですね。
都道府県ごとに設置されている、公的な機関です。
正式名称は「農地中間管理機構」
農地中間管理機構(以下、農地バンク)は農地の有効活用を目的として設置されている機関です。
基本的には売買ではなく貸し借りの仲介をしています。
若い人がせっかく農業を始めたいと思っても、まず直面する問題が農地をどう取得するかということです。
農地を使いやすくする制度
農地は食料を確保する土地であるという性質上、簡単に売買もできないですし、借りるのも難しい土地です。
しかし農業に携わる人たちの高齢化や後継者不足から、もう農家を廃業して誰かに土地を貸したいと思う人が増えています。
一方で、農業を始めてみたいけれど土地を手に入れるほどの資金もないし、貸してくれる人も見つからない、と困っている人がいます。
その間を取り持ち、農地の有効活用をしてもらおうというのが農地バンクの役割です。
また、持っている農地が分散している場合、その利用権を交換し、土地を集約するためのお手伝いもしてくれます。
飛び地(土地が離れていること)になっていると農地としては生産性が低くなってしまいます。
公的機関が農地の橋渡しをしてくれるということで安心ですし、農地バンクによって農地の集約が行われれば生産性ももっと向上するのではないかと期待されているのです。
農地をこれ以上減らさないため
農地は宅地とは違い、国にとって非常に大切な土地です。農業はどのような土地でも行えるわけではなく、良い土壌でなくてはなりません。
農作物の生産量が減少することはすなわち食料自給率の低下につながり、深刻な食料問題ともなりかねません。
そこで国を挙げて農地をなんとか有効活用しようというのが農地バンクなのです。
これ以上農地を減らさないために、農家と農家になりたい人の橋渡しをしているのです。
誰でも使えるの?農地バンクの利用方法
では、農家になりたい!と思ったら誰でも農地バンクを利用できるのでしょうか。
具体的な利用方法についてまとめましたので、将来農業をやってみたい方は覚えておくとよいでしょう。
農地貸し出しの大まかな流れ
農地バンクは貸したい農家と借りたい人の仲立ちをします。
- 農家の人が農地バンクに相談
- 申請書を提出
- 審査、貸し出し
となります。
農地バンクは農家に賃料を払い農地を借りて、その農地を農業をやりたい人に貸し出すという仕組みなのです。
農地は通常公募期間が決まっていて、年に数回、農地を借りたい人を募集しています。公募時期など詳しくは市町村のホームページを確認してください。
10年以上の貸し出し期間
農地を貸し出したいという申し出をするのはいつでもいいのですが、貸す期間については最低でも10年以上の期間が必要です。
一旦貸し出したら10年は戻ってこないということを考慮のうえで貸し出すようにしてください。
この10年という期間がネックになって、農地バンクの利用がなかなか進んでいないようです。
市町村が窓口
農地バンクの設置は都道府県ごとですが、窓口は各市町村です。
都道府県単位では範囲が広すぎるため、実際の業務は農地の実情を把握しやすい市町村単位になっているのです。
ですから貸したい人も借りたい人も、問い合わせをするなら各市町村に聞いてみてください。
農地を貸したいと申し出る
使っていない農地をなんとか活用したいという方は、市町村の窓口にまずは相談してみてください。
窓口で貸付希望申請書を提出すると農地の調査が行われます。
この時点ではまだ借り上げは決定していませんので、申請してすぐに借り手が見つかるわけではありません。
農地の調査、確認
貸付希望の申請をすると、適切な農地かどうかを農地バンクが調査します。
登記簿上は農地になっていても、耕作放棄から長年経過し、荒れ果てて農地としてすぐに使えないような状態ですと貸付ができない可能性もあります。
貸し出せるとなった場合には、貸し出す期間や賃料などの調整に入ります。
マッチング
農地の貸し出し期間や賃料が決定したところで、いよいよ借り手とのマッチングです。
この時点ではまだ、農地の管理権は所有者にあり、農地バンクは借り手を見つけるという作業をしているにすぎません。
年に数回公募をかけて借り手を募集します。申し込みがあったら希望を聞いて、条件など詳細を詰めていくのです。
賃料や賃貸期間などを話し合い、当事者同士で話がまとまらない時には間に入って交渉をします。
中間管理権の発生
条件の折り合いがついて農地を借りるということが決まれば、農地バンクに「中間管理権」という権利が発生します。
この権利によって農地バンクは農家から農地を借り受け、賃料を払います。
借りる場合の手続き
農地を借りたいと思った時の手続きは、まず年数回(6月と9月が多い)に行われている借り受け募集に応募します。
ここで、
- 借りたい時期、期間
- 農業の計画(作る予定の作物、農地を借りる理由など)
- 希望する農地の面積や場所
などを記入した申請書を提出します。
貸し手とのマッチングのために希望者の氏名や希望条件などが公表されます。
そしてうまく貸し手が見つかれば、期間などの条件交渉に移ります。
借りても貸し手も嬉しい、農地バンクを使うメリット
農家も高齢化しており、後継者不足で悩んでいますから、農地を適切に管理してくれる人がいれば嬉しいですね。
日本の食料自給率の低下は深刻な問題ですから、遊んでいる農地が活用されるなら、それは国にとってもメリットが大きいわけです。
使っていない農地を活用できる
農地バンクが借りてくれるなら、土地を無駄に遊ばせておくことはなくなりますし、有効活用して作物がたくさん作られるようになります。
農家も嬉しい、消費者も嬉しい。いいことづくめでしょう。
借り手とのマッチング
売るに売れない、では貸そうと思っても借り手を自分で見つけるのも大変です。
その点、農地バンクが間に入れば、市町村を窓口として借り手を見つけてくれるのですからとても助かります。
しかも交渉がうまくまとまらない時には間に入ってくれますし、安心ですね。
賃料を得ることができる
農地を遊ばせておくだけなら維持費だけがかかって大変ですが、農地バンクに貸し出せば賃料が入ります。
これは非常にありがたいことでしょう。
協力金は貸し付けている土地の割合や広さによって違ってきますので、詳しくは農地バンクに問い合わせてみましょう。
公的機関が間にいる安心感
土地の賃貸借は何かとトラブルがつきものです。返して欲しくても返してくれないとか、当事者同士の高尚だとうまくいかないことも多いです。
しかし間に公的機関が入っているということで、農地を直接借りているのは農地バンクなので、当事者同士でのトラブルを防ぐことができます。
増税を防ぐ
家も放置しておくと「特定空家」に認定されて税金が高くなるように、農地も耕作を放棄してそのままにしておくと、固定資産税が上がります。
何も作物を作っていない土地は農地とみなされないからです。最大1.8倍になってしまいますので、何も得をすることがありません。
しかし農地バンクに貸し出してきちんと耕作を行ってもらえれば、税金をそのままに抑えておくことができるのです。
土地を手放さなくて済む
農地を個人間で貸し借りすると、貸した土地が返ってこないというトラブルに見舞われることが少なくありません。
しかし農地バンクに貸すのであれば、最初に決めた期間を満了すれば土地は戻ってきます。
また、借り手との調整が必要ですが、土地の賃貸を再契約という形で延長することも可能なのです。
土地を遊ばせてしまっていると維持費が払えなくなって手放さなければならない人もいますが、貸している間は少なくともその心配はなくなります。
利用者が少ない?農地バンクの課題
貸す方にも借りる方にもいいことづくめに思える農地バンクなのですが、実は行政側の思ったようには利用が進んでいないというのが現状です。
それはどのようなことが原因なのでしょうか。
土地に対する愛着の問題
農地バンクを経由して農地を貸し出す場合、借り手は全国からやってくる可能性があるわけです。
古くから農業を行なっている人の中には、土地に対する愛着が強く、知らない人には貸したくないという思いがあるのです。
そのような理由でなかなか農地バンクを利用してみよう、というところまで至らないというのが現状のようです。
賃料は自由に決められない
一応、賃料については貸し手と借り手の間の交渉によって決められます。
しかし現状としては借りようとする人の方が少ないので、どうしても借り手に有利な条件で交渉が行われます。
貸し手にとってのメリット感が少ないために、なかなか利用が進まないんですね。
借り手が思うように見つからない
農地バンクに貸し出しを申請しても、必ずしも借り手が見つかる保証はありません。
一応農地バンクが公募をして貸し手を募集してくれるものの、そこは需要と供給の問題があって、借り手が使いたいと思うような土地がなければ借りてくれないわけですね。
リストに載せていても一定期間借り手が見つからなかったら、結局土地は戻ってきます。
せっかく申請したのに借り手が見つからないと、それ以降利用しようという気は起こらなくなってしまうでしょう。
借り手を選べない
土地の借り手は公募で募集しますから、どこの誰が借りるかわかりません。貸し手が「この人がいい」と選べるわけではないのです。
農家の人は土地に対する愛着が強いということは前述しましたが、借り手を選べないということも貸し手が増えない大きな原因の一つです。
狭い土地では借りてもらえない
農地バンクが借りてくれるのは、ある程度の規模が必要なので、小さな農地の場合は周辺の農家と共同して土地を集約して貸し出すということにしないと、なかなか借り手が見つからないのです。
そうなると隣家との交渉なども必要となり、貸し出しが面倒になってしまうのです。
10年という期間が長すぎる
10年以上の貸し出し期間が長いか短いか、感じ方は人それぞれですが、一度貸し出してしまうと最低でも10年は何もできないというのがネックになっています。
10年という固定された期間によってうまく活用するチャンスを逃すかもしれない、そう思う人にとってはこの期間がデメリットになってしまうんですね。
確実に使わないであろう土地は農地バンクへ
どうにかして有効活用したいと思っている人にとっては農地バンクはあまり利用価値がないかもしれません。
しかし後継者もいない、広い農地を活用する方法も思いつかないという方にとっては、ありがたい制度なのではないでしょうか。
申請して通らなかったとしてもデメリットはないわけで、借り手が見つからなければまた違う方法を考えれば良いということです。
確実にこの先10年は使わないという土地があるなら、農地バンクを活用してみませんか。







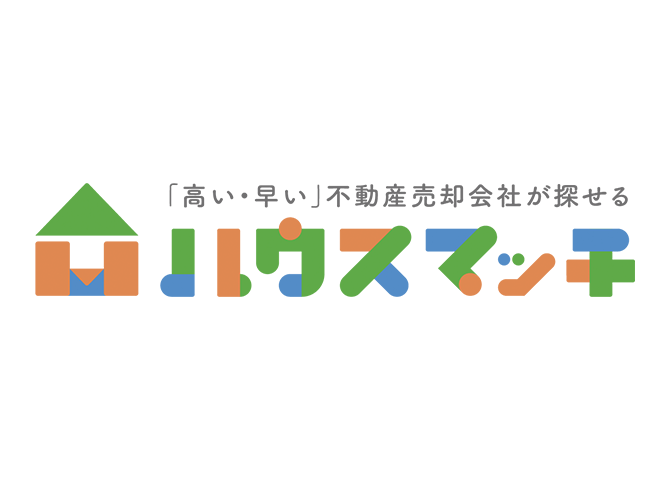
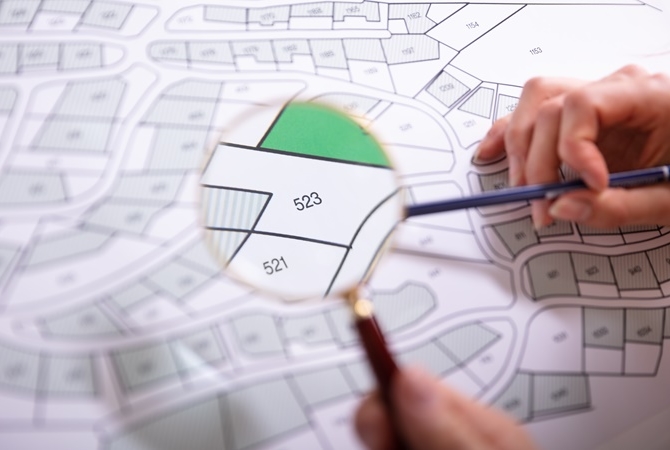



 専門のコンシェルジュがお手伝いいたします!
専門のコンシェルジュがお手伝いいたします!
